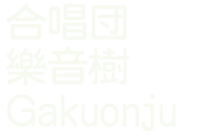樂音樹 第6回演奏会の特設ページ
おかげさまで、盛会のうちに終了いたしました。ありがとうございました。

合唱団『樂音樹』第6回演奏会
日時:2016年3月6日(日)
開演:15:00(開場:14:30 )
場所:富山県民会館ホール(アクセス)
チケット:全席自由席 一般:1,000円
学生:500円(中学生以下無料)
アーツナビインターネット販売はこちら
アーツナビのサービスカウンターでお買い求めいただけます
・富山県民会館(富山市新総曲輪4番18号)TEL076-432-3111
・富山県教育文化会館(富山市舟橋北町7-1)TEL076-441-8635
・富山県高岡文化ホール(高岡市中川園町13-1)TEL0766-25-4141
・新川文化ホール(魚津市宮津110)TEL0765-23-1123
主催:合唱団樂音樹
共演:富山少年少女合唱団
後援:富山県 富山市 富山県合唱連盟 富山県芸術文化協会
北日本新聞社 ケーブルテレビ富山
日時:2016年3月6日(日)
開演:15:00(開場:14:30 )
場所:富山県民会館ホール(アクセス)
チケット:全席自由席 一般:1,000円
学生:500円(中学生以下無料)
アーツナビインターネット販売はこちら
アーツナビのサービスカウンターでお買い求めいただけます
・富山県民会館(富山市新総曲輪4番18号)TEL076-432-3111
・富山県教育文化会館(富山市舟橋北町7-1)TEL076-441-8635
・富山県高岡文化ホール(高岡市中川園町13-1)TEL0766-25-4141
・新川文化ホール(魚津市宮津110)TEL0765-23-1123
主催:合唱団樂音樹
共演:富山少年少女合唱団
後援:富山県 富山市 富山県合唱連盟 富山県芸術文化協会
北日本新聞社 ケーブルテレビ富山
こんどのコンサートは?
第6回を数える合唱団樂音樹の演奏会。今回のコンサートは意欲的な構成となっています。
「楽しみながら成長したい」という思い・・・、少し欲張り過ぎているかもしれません。今歌いたいもの、お聴かせしたい曲を全部詰め込みました(笑)
富山県内では珍しい児童合唱とのコラボレーションも、樂音樹の新たなチャレンジです。
昨年は開場が狭かったという声も多くいただき、今回は「富山県民会館ホール」なので座席はたくさんあります。ぜひ多くの方々にお越しいただきたいと思います。
「楽しみながら成長したい」という思い・・・、少し欲張り過ぎているかもしれません。今歌いたいもの、お聴かせしたい曲を全部詰め込みました(笑)
富山県内では珍しい児童合唱とのコラボレーションも、樂音樹の新たなチャレンジです。
昨年は開場が狭かったという声も多くいただき、今回は「富山県民会館ホール」なので座席はたくさんあります。ぜひ多くの方々にお越しいただきたいと思います。
プログラムと見どころ聴きどころ
第1ステージ 祈りのアカペラ曲
・Ave Maria 作曲:J.G. Rheinberger
・Salve Regina 作曲:J.G. Rheinberger
・Missa Simplex Ⅱ 作曲:R.Dubra
指揮:森井 淳
今回、唯一のアカペラ、そしてラテン語のステージです。
ヨーゼフ・ガブリエル・ラインベルガー(1839-1901)はドイツで活躍した作曲家です。教会オルガニストでもあり、多くのオルガン曲、そして宗教合唱曲を残しています。生前は大人気だったようですが、その古典的、保守的とも言える作風からか、徐々にその作品は忘れ去られていったといいます。
その後、その美しいメロディーと共に、再評価の動きが起こり、今では日本でも多くの合唱団が演奏しています。
今回、「Ave Maria(しあわせな方、マリア)」「Salve Regina(元后あわれみの母)」2曲の聖母マリアにまつわる曲を選びました。
ラトビア出身のリハルト・デュブラ(1964-)は、まさしく今、同じ時代を生きる作曲家。
決して難解な音楽ではありません。敬虔なカトリック信者であるデュブラは、最小限の音で最大限の効果「聖なるミニマリズム」を目指していたといい、彼の音楽は、ときにはヒーリング音楽として捉えられるくらいに、とても純粋で美しい響きを持ちます。
「Missa Simplex Ⅱ」は、ミサのKyrie〜Gloria〜Sanctus〜AgnusDeiの4曲がコンパクトに納めれられています。
「私が音楽を創り出しているのではなく、私に送られてくる音楽を書き留めているだけだ」(デュブラ)
2人の、美しいアカペラ宗教音楽をお楽しみください。
・Salve Regina 作曲:J.G. Rheinberger
・Missa Simplex Ⅱ 作曲:R.Dubra
指揮:森井 淳
今回、唯一のアカペラ、そしてラテン語のステージです。
ヨーゼフ・ガブリエル・ラインベルガー(1839-1901)はドイツで活躍した作曲家です。教会オルガニストでもあり、多くのオルガン曲、そして宗教合唱曲を残しています。生前は大人気だったようですが、その古典的、保守的とも言える作風からか、徐々にその作品は忘れ去られていったといいます。
その後、その美しいメロディーと共に、再評価の動きが起こり、今では日本でも多くの合唱団が演奏しています。
今回、「Ave Maria(しあわせな方、マリア)」「Salve Regina(元后あわれみの母)」2曲の聖母マリアにまつわる曲を選びました。
ラトビア出身のリハルト・デュブラ(1964-)は、まさしく今、同じ時代を生きる作曲家。
決して難解な音楽ではありません。敬虔なカトリック信者であるデュブラは、最小限の音で最大限の効果「聖なるミニマリズム」を目指していたといい、彼の音楽は、ときにはヒーリング音楽として捉えられるくらいに、とても純粋で美しい響きを持ちます。
「Missa Simplex Ⅱ」は、ミサのKyrie〜Gloria〜Sanctus〜AgnusDeiの4曲がコンパクトに納めれられています。
「私が音楽を創り出しているのではなく、私に送られてくる音楽を書き留めているだけだ」(デュブラ)
2人の、美しいアカペラ宗教音楽をお楽しみください。
第2ステージ 「あめつちのうた」富山少年少女合唱団ステージ
童声(女声)合唱組曲 「あめつちのうた」より
1.空のうた
2.樹のうた
3.風のうた
作詩:林 望 作曲:上田 真樹
指揮:廣本浩太 ピアノ:天池千鶴子
富山を代表する児童合唱団によるステージ(「・・・これから代表する合唱団になります」と謙遜されていましたが)。曲のテーマである空、樹、風を、子どもたちが大切に感じながら歌いあげます。
「歌ってくれる子供たちに、とにかく音楽を全身で楽しんでもらいたい。その音楽を通して、空や、水や、風や…たくさんのものを感じてほしい。これからの未来を担う子供たちには、それらを愛して大切にしていってもらいたい。そしてそんな歌声が、聴いている人の心にも届いて欲しい。」(上田真樹)
1.空のうた
2.樹のうた
3.風のうた
作詩:林 望 作曲:上田 真樹
指揮:廣本浩太 ピアノ:天池千鶴子
富山を代表する児童合唱団によるステージ(「・・・これから代表する合唱団になります」と謙遜されていましたが)。曲のテーマである空、樹、風を、子どもたちが大切に感じながら歌いあげます。
「歌ってくれる子供たちに、とにかく音楽を全身で楽しんでもらいたい。その音楽を通して、空や、水や、風や…たくさんのものを感じてほしい。これからの未来を担う子供たちには、それらを愛して大切にしていってもらいたい。そしてそんな歌声が、聴いている人の心にも届いて欲しい。」(上田真樹)
第3ステージ ヒット曲メドレー「HANA」
混声合唱のためのヒットメドレー「HANA」
花 (武島羽衣/滝廉太郎)
サボテンの花 (財津和夫)
さくら (森山直太朗)
ハナミズキ (一青窈/マシコタツロウ)
リンゴ追分 (小沢不二夫/米山正夫)
世界に一つだけの花(槇原敬之)
赤いスイートピー (松本隆/呉田軽穂)
花 (喜納昌吉)
編曲:三沢治美
指揮:重松秀子 ピアノ:新村真理
「花」にまつわる曲。日本のPOPS史上、時代を超えて長く愛され歌われる「名曲」の数々です。
「歌い手の皆様が自分らしい笑顔に満ちた「歌のHANA」を、
聴く人々の心に、可憐にそして温かく咲かせゆくことを、心より願いつつ・・・」(三沢治美)
樂音樹のシンボルでもある重松秀子が教員時代、教え子たちに毎年送り続けた言葉が「楽」でした。
純粋に、仲間と音楽をする喜び、楽しみを味わえるステージとなることでしょう。
ピアノは樂音樹のアイドルになりつつある新村真理。いつも笑顔のコンビです。
花 (武島羽衣/滝廉太郎)
サボテンの花 (財津和夫)
さくら (森山直太朗)
ハナミズキ (一青窈/マシコタツロウ)
リンゴ追分 (小沢不二夫/米山正夫)
世界に一つだけの花(槇原敬之)
赤いスイートピー (松本隆/呉田軽穂)
花 (喜納昌吉)
編曲:三沢治美
指揮:重松秀子 ピアノ:新村真理
「花」にまつわる曲。日本のPOPS史上、時代を超えて長く愛され歌われる「名曲」の数々です。
「歌い手の皆様が自分らしい笑顔に満ちた「歌のHANA」を、
聴く人々の心に、可憐にそして温かく咲かせゆくことを、心より願いつつ・・・」(三沢治美)
樂音樹のシンボルでもある重松秀子が教員時代、教え子たちに毎年送り続けた言葉が「楽」でした。
純粋に、仲間と音楽をする喜び、楽しみを味わえるステージとなることでしょう。
ピアノは樂音樹のアイドルになりつつある新村真理。いつも笑顔のコンビです。
第4ステージ 2015コンクール報告ステージ
(課題曲)「ねむりのもりのはなし」
作詩:長田 弘 作曲:山下祐加
(自由曲)「ヨハネによる福音」より「Ⅰ.初めにみことばがあった」
作曲:髙田三郎
指揮:森井 淳 ピアノ:竹内佳代(客演)
中部コンクールの再演となります。
(課題曲)
話題の若手女性作曲家山下祐加さんと、多くのファンを持った詩人長田弘氏。長田氏は、山下祐加さんによるこの曲が、実際に歌われるのを楽しみにしたおられたようですが、残念ながら2015年5月に亡くなりました。
「いまはむかし あるところに あべこべのくにがあったんだ」
「つよいものが もろい もろいのが つよい」
「ただしいがまちがっていて まちがいが ただしかった」
「うそが ほんとのことで ほんとのことが うそだった」
平易でしかもユーモラスでもある言葉で語られる「あべこべのくに」、言葉の概念やリズミカルな言い回しが活かされながら、社会にそして私たちに深く問いかけています。
告白すると、今回は例年以上に課題曲にじっくり取り組むことになりました。
その最大の理由は、作曲家自身が「調性、リズム、音程、アーティキュレーションなどさまざまな角度から『あべこべのせかい』を演出した」と語るこの曲が、樂音樹にとって「難しかったこと」です。とくにリズムについては、これまでの課題曲の中でも特に難曲の部類に入るのではないでしょうか。
それが徐々にこの音楽世界に惹きこまれ、心地良くなってきたことを団員の多くが体験し、それまでの苦労も本番直前には大きな喜びに変わりました。ほんの少し成長させてもらった気がします。
後日、私たちの演奏録音を山下さんに聴いていただきました。丁寧なお返事をいただき、樂音樹に山下祐加ファンが一気に増えたようです。
(自由曲)
髙田三郎作曲の「水のいのち」は今もなお、日本で最も歌われている合唱曲だろうと思います。
一方、カトリック信者であった髙田三郎氏は、教会のミサがラテン語ではなくそれぞれの母国語で行われるようになってから、教会で歌われる多くの日本語典礼聖歌を作曲した功績により、バチカンから聖シルベストロ教皇騎士団勲章を授与されています。「ヨハネによる福音」は、氏の聖書三部作の1つですが、70歳を超えての作品とは思えない、現代的手法も取り入れたスケールの大きな作品です。
作曲者は、「人知をはるかに超えるもの、新約のキリストについて書くことの無謀さ」そして、「及ばずとはいえ、そのほんの一端をでもという思いに支えられて書き進め、演奏し続けてきた」といいます。
日本の合唱界を牽引した圧倒的な存在感。髙田作品にはすでに多くの名演奏があるため、むしろ「コンクール」で「勝つ」には難しいと言われることもあります。
幸い(?)まだまだ賞を目的にできない樂音樹にとっては、純粋に、この素晴らしい作品にじっくり取り組み、向き合うことができました。
余談となりますが、最初の日本語訳聖書といわれるギュツラフ訳聖書の冒頭がまさしくこの「ハジマリニ カシコイモノゴザル」であり、じつは長田弘氏が、この部分をテーマにした詩を書いています。
そして、東日本大震災の直後、NHKで自作5編の詩を紹介されているのですが、4つ目が「ねむりのもりのはなし」、そして続く最後の詩が、この「カシコイモノヨ、教えてください」でした。
話題の若手女性作曲家山下祐加氏、そして大家髙田三郎氏の晩年の大作「ヨハネによる福音」。
作風の全く異なる2曲ですが、「真実」を問い、それに呼応するかのような「恵みと真理」の讚歌の組み合わせ、この選曲を私たちは気に入っています。
作詩:長田 弘 作曲:山下祐加
(自由曲)「ヨハネによる福音」より「Ⅰ.初めにみことばがあった」
作曲:髙田三郎
指揮:森井 淳 ピアノ:竹内佳代(客演)
中部コンクールの再演となります。
(課題曲)
話題の若手女性作曲家山下祐加さんと、多くのファンを持った詩人長田弘氏。長田氏は、山下祐加さんによるこの曲が、実際に歌われるのを楽しみにしたおられたようですが、残念ながら2015年5月に亡くなりました。
「いまはむかし あるところに あべこべのくにがあったんだ」
「つよいものが もろい もろいのが つよい」
「ただしいがまちがっていて まちがいが ただしかった」
「うそが ほんとのことで ほんとのことが うそだった」
平易でしかもユーモラスでもある言葉で語られる「あべこべのくに」、言葉の概念やリズミカルな言い回しが活かされながら、社会にそして私たちに深く問いかけています。
告白すると、今回は例年以上に課題曲にじっくり取り組むことになりました。
その最大の理由は、作曲家自身が「調性、リズム、音程、アーティキュレーションなどさまざまな角度から『あべこべのせかい』を演出した」と語るこの曲が、樂音樹にとって「難しかったこと」です。とくにリズムについては、これまでの課題曲の中でも特に難曲の部類に入るのではないでしょうか。
それが徐々にこの音楽世界に惹きこまれ、心地良くなってきたことを団員の多くが体験し、それまでの苦労も本番直前には大きな喜びに変わりました。ほんの少し成長させてもらった気がします。
後日、私たちの演奏録音を山下さんに聴いていただきました。丁寧なお返事をいただき、樂音樹に山下祐加ファンが一気に増えたようです。
(自由曲)
髙田三郎作曲の「水のいのち」は今もなお、日本で最も歌われている合唱曲だろうと思います。
一方、カトリック信者であった髙田三郎氏は、教会のミサがラテン語ではなくそれぞれの母国語で行われるようになってから、教会で歌われる多くの日本語典礼聖歌を作曲した功績により、バチカンから聖シルベストロ教皇騎士団勲章を授与されています。「ヨハネによる福音」は、氏の聖書三部作の1つですが、70歳を超えての作品とは思えない、現代的手法も取り入れたスケールの大きな作品です。
作曲者は、「人知をはるかに超えるもの、新約のキリストについて書くことの無謀さ」そして、「及ばずとはいえ、そのほんの一端をでもという思いに支えられて書き進め、演奏し続けてきた」といいます。
日本の合唱界を牽引した圧倒的な存在感。髙田作品にはすでに多くの名演奏があるため、むしろ「コンクール」で「勝つ」には難しいと言われることもあります。
幸い(?)まだまだ賞を目的にできない樂音樹にとっては、純粋に、この素晴らしい作品にじっくり取り組み、向き合うことができました。
余談となりますが、最初の日本語訳聖書といわれるギュツラフ訳聖書の冒頭がまさしくこの「ハジマリニ カシコイモノゴザル」であり、じつは長田弘氏が、この部分をテーマにした詩を書いています。
そして、東日本大震災の直後、NHKで自作5編の詩を紹介されているのですが、4つ目が「ねむりのもりのはなし」、そして続く最後の詩が、この「カシコイモノヨ、教えてください」でした。
話題の若手女性作曲家山下祐加氏、そして大家髙田三郎氏の晩年の大作「ヨハネによる福音」。
作風の全く異なる2曲ですが、「真実」を問い、それに呼応するかのような「恵みと真理」の讚歌の組み合わせ、この選曲を私たちは気に入っています。
第5ステージ 「いのちの木を植える」児童合唱との合同ステージ
混声合唱とピアノのための「いのちの木を植える」
1.樹下
2.梨の木
3.木
4.木を植える
作詩:谷川俊太郎 作曲:木下牧子
指揮:森井 淳 ピアノ:竹内佳代(客演)
共演:富山少年少女合唱団
2012年7月の大阪シンフォニーホール、豊中混声合唱団演奏会で初めてこの曲を聴きました。児童合唱を加えた演奏、涙が止まらなくなってしまうほど感動的なステージで、以来、いつか富山で実現できたらと思っていました。
終曲の「木を植える」は、児童合唱がくっきり活躍できるよう豊中混声が木下牧子氏にさらに編曲委嘱されたのですが、今回は、木下牧子氏、豊中混声合唱団常任指揮者の西岡茂樹氏の快諾をいただき、こちらの編曲版での演奏となります。
今回、富山少年少女合唱団さんと共演できることを幸せに感じています。
また今回、親子での出演者がいることもさらに嬉しく、羨ましくも思います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◇詩人谷川俊太郎氏のことば◇
『木を植える
それは夢見ること
子どもたちのすこやかな明日を』
「僕は木漏れ日や木陰というものが好きなんですね。木の陰に座るとか木漏れ日の中にいるとか、そうしたことが好きなので、子どもたちが木陰で遊んでいる、木漏れ日を浴びながら遊んでいるというイメージが常に頭の中にあるんです(笑い)。ですから木のないところに木を植えれば、必ず長い年月が経つうちに木漏れ日や木陰をつくってくれるだろう。今植えた木は、いずれ未来の子どもたちのために木陰や木漏れ日をつくってくれるだろう。そういうことを自分ではイメージして、この部分を書きました」
〜(省略)〜
『木を植える
それは知恵 それは力
生きとし生けるものをむすぶ』
「人の生活と木は切っても切れない関係にあります。植えるにしても手入れはしていかないといけないし、切るなら切った分を復元していかないといけない。どちらにしてもやりっぱなしのままだからツケがきているんでしょうね。
また僕たちの生活や暮らしというものは何かを犠牲にしながら成り立っている。そのことを意識するかどうかが、この先の大きな分かれ道をいう気がします」
「木を植えるということが、たとえば子どもと大人を結ぶし、中国の人と日本の人を結ぶ。そのような人間同士を結ぶし、エコロジカルにいえば小さな他の植物や生物を木は活かしているわけですから、いのち全体を結ぶものであるともいえます。木を植えていけば、木というものを仲介にしていのちが動いていることを実感できると思うんです。人間だって、大きな文明を想像して偉そうな顔をしているけれど、実際は木と同じような生命であることを感じてもらえるんじゃないかなと思います」
谷川俊太郎×岡田卓也「いのちの木を植える」(マガジンハウス)より抜粋
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1.樹下
2.梨の木
3.木
4.木を植える
作詩:谷川俊太郎 作曲:木下牧子
指揮:森井 淳 ピアノ:竹内佳代(客演)
共演:富山少年少女合唱団
2012年7月の大阪シンフォニーホール、豊中混声合唱団演奏会で初めてこの曲を聴きました。児童合唱を加えた演奏、涙が止まらなくなってしまうほど感動的なステージで、以来、いつか富山で実現できたらと思っていました。
終曲の「木を植える」は、児童合唱がくっきり活躍できるよう豊中混声が木下牧子氏にさらに編曲委嘱されたのですが、今回は、木下牧子氏、豊中混声合唱団常任指揮者の西岡茂樹氏の快諾をいただき、こちらの編曲版での演奏となります。
今回、富山少年少女合唱団さんと共演できることを幸せに感じています。
また今回、親子での出演者がいることもさらに嬉しく、羨ましくも思います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◇詩人谷川俊太郎氏のことば◇
『木を植える
それは夢見ること
子どもたちのすこやかな明日を』
「僕は木漏れ日や木陰というものが好きなんですね。木の陰に座るとか木漏れ日の中にいるとか、そうしたことが好きなので、子どもたちが木陰で遊んでいる、木漏れ日を浴びながら遊んでいるというイメージが常に頭の中にあるんです(笑い)。ですから木のないところに木を植えれば、必ず長い年月が経つうちに木漏れ日や木陰をつくってくれるだろう。今植えた木は、いずれ未来の子どもたちのために木陰や木漏れ日をつくってくれるだろう。そういうことを自分ではイメージして、この部分を書きました」
〜(省略)〜
『木を植える
それは知恵 それは力
生きとし生けるものをむすぶ』
「人の生活と木は切っても切れない関係にあります。植えるにしても手入れはしていかないといけないし、切るなら切った分を復元していかないといけない。どちらにしてもやりっぱなしのままだからツケがきているんでしょうね。
また僕たちの生活や暮らしというものは何かを犠牲にしながら成り立っている。そのことを意識するかどうかが、この先の大きな分かれ道をいう気がします」
「木を植えるということが、たとえば子どもと大人を結ぶし、中国の人と日本の人を結ぶ。そのような人間同士を結ぶし、エコロジカルにいえば小さな他の植物や生物を木は活かしているわけですから、いのち全体を結ぶものであるともいえます。木を植えていけば、木というものを仲介にしていのちが動いていることを実感できると思うんです。人間だって、大きな文明を想像して偉そうな顔をしているけれど、実際は木と同じような生命であることを感じてもらえるんじゃないかなと思います」
谷川俊太郎×岡田卓也「いのちの木を植える」(マガジンハウス)より抜粋
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(森井 淳)
ゲストの紹介
共演:富山少年少女合唱団

平成27年4月、富山児童合唱団と富山東部児童合唱団が一つになり、富山少年少女合唱団となりました。「合唱を通して子供たちの健全な育成」を目標に廣本浩太氏指導の下、富山市立東部児童館の合唱クラブとして活動しており、富山市内の「歌が大好き」な小・中学生が日々練習に励んでいます。定期演奏会の開催やクロネコファミリーコンサートにて京都市交響楽団と共演するなど様々なイべントに出演し、地域に根ざした合唱団を目指しています。
毎月第1・3・4日曜日の9:45〜11:15の間練習を行っているので、一緒に歌いたい方は気軽に足を運んでみてください。詳しくは、「富山市立東部児童館 076-421-4212」まで問い合わせください。
毎月第1・3・4日曜日の9:45〜11:15の間練習を行っているので、一緒に歌いたい方は気軽に足を運んでみてください。詳しくは、「富山市立東部児童館 076-421-4212」まで問い合わせください。
客演ピアノ:竹内佳代

桐朋学園大学ピアノ科卒業。ピアノを大坪亮子、川島伸達、松本清、伴奏法を松本明子の各氏に師事。在学中に第3回中部ショパン学生コンクール大学生部門金賞・中日賞受賞。これまで富山・浜松・名古屋でリサイタルを開催。ソロ活動、室内楽、伴奏など幅広い演奏活動を展開。現在桐朋学園大学附属「子供のための音楽教室」富山教室講師。